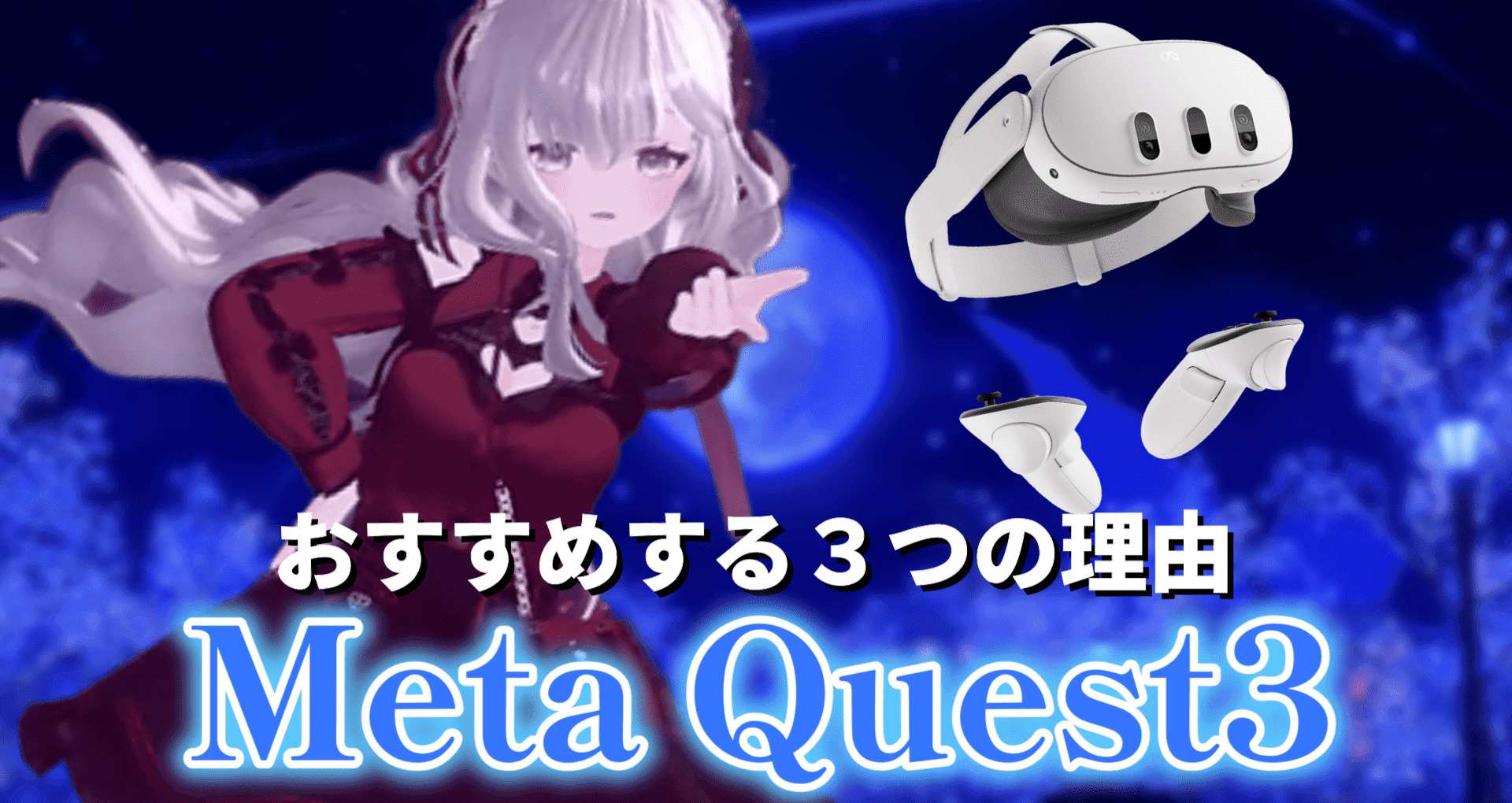メタバースの失敗は本当? 9割が計画通りに進まなかった理由と、これからの可能性

近年、大きな注目を集めたメタバース。でも最近「メタバースって、もしかして失敗だったんじゃ…」なんて声が、ちらほら聞こえてくるようになりました。
実際に、メタバースに挑戦した事業の9割が計画通りに進んでいない、という少し寂しいデータもあり「あの熱狂はどこへ?もうオワコンなのかな…」と感じている方も、きっと少なくないはずです。
かつてのセカンドライフが直面した壁を思い出し「どうして普及しないんだろう?」「本当に誰もやっていないの?」と疑問に思うのも、無理はありませんよね。
この記事では「メタバースは失敗」と言われてしまう理由を一緒に深掘りし、具体的な事例や課題を一つひとつ見ていきたいと思います。
その上で、これからの可能性や、ビジネスでメタバースを活かすための成功の鍵はどこにあるのかを、専門的な視点から、心を込めて分かりやすく解説していきます。
- メタバースが「失敗」と言われてしまう、本当のところ
- 昔の失敗と、今ぶつかっている壁の違い
- ビジネスで「うまくいった!」と「うまくいかなかった…」の分かれ道
- メタバース市場の、これからの成長ストーリー
なぜメタバースは失敗と言われるのか
9割の事業が計画通りに進まなかった、という現実

メタバースが「失敗」と言われてしまう大きな理由の一つに、事業として成り立たせることの難しさがあります。
株式会社クニエが2023年に行った調査によると、メタバース事業に取り組んだ企業のうち、なんと91.9%が「事業化に向けた検討が止まってしまった」あるいは「検討そのものをやめてしまった」という結果が出た、と報告されています(参照:メタバースビジネス調査レポート)
「メタバース」という言葉のキラキラしたイメージとは裏腹に、ビジネスとして花開かせることの厳しさを示す、少しショッキングなデータですよね。
この調査では、うまくいかなかった事業の多くが、企画内容やビジネスモデルの詰めが甘かったり、検討の進め方が整っていなかったり、そしてプロジェクトを引っ張っていく体制が弱かったり、といった共通の課題を抱えていたことも分かってきました。
例えば「なんだか流行っているみたいだから」という、ちょっぴりフワッとした理由でスタートしてしまったり、どうやって利益につなげるかの具体的な道のりが見えないまま、見切り発車してしまったりするケースが後を絶たないのです。
このように、挑戦した事業の9割以上が計画通りに進んでいないという現実は「メタバースは儲からない」「ビジネスとしては難しい」という印象を、世の中に広く与える一因となってしまっています。
メタバースは本当に「オワコン」なの?

「メタバースはオワコン(終わったコンテンツ)だよね」という言葉を、耳にする機会が増えたように感じます。
特に、Meta社(旧Facebook)がメタバース事業で大きな赤字を出したことや、一時期の熱狂的な報道が落ち着いたことから「ブームはもう去ったんだ」と考える人も少なくありません。
でも、メタバース市場そのものが終わりを迎えた、と結論づけるのは、まだ少し早いのかもしれません。
矢野経済研究所の調査によれば、日本のメタバース市場規模は2023年度に1,863億円となり、前の年度からなんと135.2%も成長しています(参照:メタバースの国内市場動向調査を実施(2024年))
さらに、2027年度には1.2兆円を超える規模にまで成長する、と予測されているのです。これは、普通の成長産業を大きく上回る、目を見張るような成長率。多くの企業がその未来を信じて、投資を続けている証拠とも言えそうです。
IT分野でよく使われるガートナー社の「ハイプ・サイクル」という考え方に当てはめてみると、現在のメタバースは、期待だけが先行する「過度な期待のピーク期」を通り過ぎ、課題がハッキリと見えてくる「幻滅期」という、少ししょんぼりしてしまう時期にいる、と考えることができます。
【パイプサイクル2023が発表】
ガートナーが日本のハイプ・サイクルの2023年版を発表しました。
・生成AIは過度な期待のピーク
・メタバースは幻滅期の底
・web3はまだ幻滅期の下降中
という整理のようです。… pic.twitter.com/e12oCCjsng— 亀岡 千泰 / Z Venture Capital (@ChihiroKameoka) August 19, 2023
これは、新しい技術が大人へと成長し、社会に根付く前に多くの技術が経験する、いわば成長痛のような段階です。
この少し寂しい時期を乗り越え、実用的な価値がみんなに認められる「生産性の安定期」へと向かう可能性を秘めているため「オワコン」とバッサリ切り捨ててしまうのは、まだ早いのではないでしょうか。
「誰もやってない…」と言われるほどの、寂しい現状

「メタバースにログインしてみたけど、誰もいない…」
「人がいなくて、なんだか寂しいな」
そんな声は、ユーザーさんが離れてしまう大きな原因の一つであり「誰もやってない」というイメージにつながってしまっています。
この現象は「メタぼっち」なんて、ちょっと切ない言葉も生まれているくらいで、特に新しく生まれたプラットフォームでよく見られる光景です。
この問題の背景には、いくつかの理由が考えられます。
プラットフォームが乱立し、ユーザーが分散してしまった
今、世界中には数えきれないほどのメタバースプラットフォームが存在します。
それぞれが独自のコミュニティを作ろうと頑張っていますが、結果としてユーザーさんがあちこちに散らばってしまい、一つの場所に十分な人が集まりにくい状況が生まれています。
たとえ広大なワールドを用意しても、同時にアクセスしている人が少なければ、誰かと出会うチャンスはぐっと減ってしまいますよね。
「ここで何すればいいの?」という目的の欠如
多くのメタバースでは、「広い世界にポンと一人…ここで何をすればいいんだろう?」と、途方に暮れてしまうような問題も指摘されています。
ただ空間が用意されているだけで、ユーザーの心を引きつけ、そこに「居たい」と思わせるような魅力的なコンテンツや目的が足りないと、すぐに飽きられてしまうのです。
一方で「VRChat」や「Roblox」「Fortnite」のように、すでに何億人もの巨大なユーザーコミュニティができていて、毎日活発な交流が行われている場所もちゃんと存在します。
そこでは、ユーザー自身が面白いコンテンツを生み出したり、大きなイベントが開かれたりと、自然と人が集まる仕組みができあがっています。
ですから「誰もやってない」のではなくて「人が集まる人気の場所と、そうでない場所がはっきり分かれてきている」というのが、今のリアルな姿なのかもしれませんね。
ちょっぴり苦い思い出?失敗例として語られるセカンドライフ

Wikipediaより Live radio hour in Second Life with Draxtor Despres and Jo Yardley 著作者「HyacintheLuynes」 CC BY-SA 3.0
メタバースの歴史を語る時、2000年代に一世を風靡した「セカンドライフ」は「昔、ああいうのがあってね…」と、象徴的な失敗例としてよく引き合いに出されます。
2003年に生まれたこのプラットフォームは、自分の分身であるアバターを介して仮想空間で他の人と交流したり、独自の経済圏でお商売をしたりできる、とても画期的なものでした。
2007年頃には世界中でブームになり、多くの企業やメディアが「これが未来のインターネットだ!」と注目したのです。
でも、残念ながらその熱狂は、長くは続きませんでした。勢いがなくなってしまった主な原因としては、こんなことが挙げられます。
- 高すぎる技術の壁
- 複雑すぎる操作
- 時代の風向きの変化
当時の普通のパソコンの性能では快適に動かすのが難しく、映像がカクカクしたり、動きが遅れたりすることがしょっちゅうでした。
初心者には操作が難しく、仮想空間に慣れる前に「もういいや…」と諦めてしまう人がたくさんいました。
FacebookやTwitterといった、もっと手軽に楽しめるSNSが登場し、人々のオンラインでのコミュニケーションの中心が、そちらへ移っていったのです。
これらの要因が重なり、セカンドライフは少し可哀想な「失敗したメタバース」というレッテルを貼られてしまうことになりました。
ただし、セカンドライフが完全に消えてしまったわけではありません。今でも数十万人のアクティブユーザーがいて、特定の目的を持つコミュニティや、大学の授業などで根強く使われ続けているんです。
この先輩の経験から私たちが学べるのは「技術がまだ追いついていないのに期待だけが先走ってしまうのは危ないよ」ということ。
そして同時に「心からそれを必要としている人たちがいるなら、サービスは生き続けられるんだ」という、希望の持てる教訓でもあります。
今のメタバースが同じ轍を踏まないためには、この過去の経験をしっかり見つめ直すことが、きっと大切なのでしょう。
メタバースが普及しない根本的なワケ

メタバースが、一部の熱心なファンを除いて、爆発的にみんなの生活に広まっていない背景には、いくつかの根っこにある理由が、まるで知恵の輪のように複雑に絡み合っています。
これらは主に、技術的なこと、経済的なこと、そして社会的なこと、という3つの側面から見ることができます。
- 技術的な理由
- 経済的な理由
- 社会的な理由
これまで見てきたように、質の高いメタバース体験には、高性能なパソコンやVRデバイス、そして安定した速いインターネット回線が必要です。
特に、キレイな3Dグラフィックスをリアルタイムで表示し、大勢のユーザーと同時に楽しむには、膨大な量のデータをやり取りしなければなりません。
今の通信インフラでは、住んでいる場所や時間帯によって、体験の質が変わってしまうことも…。もっと快適に楽しむには、5Gのさらなる普及や、その先の6Gといった新しい技術の登場を、もう少し待つ必要がありそうです。
本格的なVRヘッドセットは、数万円から時には数十万円もします。これは、一般の人が「ちょっと試してみようかな」と気軽に買えるお値段とは、まだ言えないかもしれません。
また、企業がメタバース空間を作って維持していくためにも、たくさんの開発コストや運営コストがかかります。
その投資に見合うだけの「儲けの仕組み」がまだ確立されていないため、多くの企業が「本当に大丈夫かな…?」と、参入にためらいを感じてしまうのも無理はありません。
メタバースの中での個人情報の扱いや、アバターを通じたいじめや嫌がらせ、著作権の問題など、法律やルール作りがまだ追いついていない点も、普及をためらわせる一因です。
ユーザーが安心して活動できるルール作りが、急いで求められています。また、やっぱり顔と顔を合わせるコミュニケーションを大切にする文化的な背景から、仮想空間での交流に、なんとなく心理的な抵抗を感じる人がまだまだ多いというのも、見過ごせない事実です。
こうした課題を一つひとつ、丁寧にほどいていかない限り、メタバースがスマートフォンやSNSのように、誰もが当たり前に使う未来は、まだ少し先のことになりそうです。
お値段も性能も…デバイスが抱える技術的なハードル
メタバースの世界に飛び込むのをためらわせる、一番分かりやすいハードルが、たぶん「機械」の問題ですよね。
特に、まるでその場にいるかのような深い没入感を味わいたい時に必要になるVR/ARヘッドセットは、価格の面でも、技術の面でも、まだまだ多くの課題を抱えています。
例えば、2023年に発売されたMeta社の「Meta Quest 3」は、比較的手に取りやすい価格でありながら性能もアップしましたが、それでも約8万円の出費が必要です。
さらに、2024年に登場して大きな話題を呼んだAppleの「Apple Vision Pro」。その圧倒的な性能と体験の質は素晴らしいものでしたが、そのお値段はなんと約50万円!
さすがに「ちょっと試してみようかな」という気持ちで手を出すのは、なかなか勇気がいりますよね。
また、お値段だけでなく、技術的な使い心地もまだ発展途上です。今のVRヘッドセットは、数年前に比べればずっと軽くて小さくなったとはいえ、長時間つけていると重さや、締め付けられる感じが気になることもあります。
さらに、映像のズレや遅れによって、乗り物酔いに似た症状(VR酔い)を感じてしまう人も少なくなく、これが、せっかく始めたのに「もういいかな…」と、続けるのをやめてしまう理由の一つになっているんです。
自分の分身であるアバターの表現力も、まだまだ成長の途中です。顔のちょっとした表情の変化や、体の自然な動きを完全に再現するところまではいっておらず、会話をしていても、ちょっとした表情のニュアンスが伝わらなくて、なんだかギクシャクしたコミュニケーションになってしまうこともあります。
こうした機械にまつわる課題が解決されて、スマートフォン並みの手軽さと快適さが実現されない限り、メタバースがみんなに当たり前に使われるようになる「マスアダプション」への道のりは、まだ少し長そうです。
メタバースの失敗の経験から見えてくる、未来のカタチ

企業がメタバースでつまずいてしまう、よくあるパターン
たくさんの企業が「メタバースで何か新しいことができるかも!」と期待を胸に、この新しい世界へ飛び込みました。でも、残念ながら、そのすべてが順風満帆というわけではないようです。
むしろ、具体的な成果を出す前に、活動を縮小したり、撤退したりするケースが目立っています。そうした、ちょっぴり残念な結果になってしまったケースには、いくつかの共通したパターンがあるんです。
- 「誰のために、何を届けたいか」がフワッとしたままのスタート
- 一度きりの「お祭り」で終わってしまう
- 最新技術に夢中になるあまり、使う人の気持ちを置き去りに…
いちばん多く見られるのが「メタバースが流行っているから」という理由だけで、はっきりとした目的や「こんな人に届けたい!」というターゲットを決めずに始めてしまうケースです。
誰に、どんな素敵な価値を届けたいのかが曖昧なままでは、ユーザーさんの心に「刺さる」ようなコンテンツは、なかなか生まれませんよね。
結果として、一時的に話題にはなっても、誰もいない「ゴーストタウン」のような、寂しい仮想空間が生まれてしまうんです。
新商品のプロモーションや発表会のために、立派なメタバース空間を作っても、そのイベントが終わった後、誰も訪れることなく放置されてしまう…。そんなケースも少なくありません。
メタバースの本当の魅力は、一回きりのお祭り騒ぎではなく、人と人とが継続的につながるコミュニティを育んだり、ファンとの絆を深めたりするところにあるはず。
一度きりのイベントに大きなお金をかけるだけでは「あれ…かけた費用の割には…」と、ちょっぴり寂しい結果に終わってしまう可能性が高いのです。
最新の3D技術や、キラキラした派手な演出にこだわるあまり、ユーザーさんにとっての「使いやすさ」や「楽しさ」といった、一番大切なことを見失ってしまうこともあります。
操作が複雑だったり、ものすごく高性能なパソコンがないと動かなかったりすると、せっかく興味を持ってくれた人さえも「なんだか難しそうだから、やめておこうかな…」と、参加を諦めてしまいます。
海外の例ですが、あのウォルト・ディズニーが大きな期待と共に立ち上げたメタバース専門の部署を、事業の再編成の中で、たった1年ほどで解散してしまったのは、私たちにとっても考えさせられる出来事でした(参照:米ディズニー、メタバース部門を解体 事業再編の一環で)
これは、メタバース事業で短期的に利益を出すことが、いかに難しいかを物語っています。
これらの経験から、成功のためには、長い目で見た視点と、じっくり考え抜かれた丁寧な戦略が、絶対に欠かせないことが分かりますね。
「これじゃなきゃ!」と思えるコンテンツが、まだ足りない?
現在のメタバースが、なかなか爆発的に広まらない大きな理由として「これのためなら!」と思わせてくれるような「キラーコンテンツ」が、まだ足りないことが挙げられます。
キラーコンテンツというのは「このコンテンツを体験したいから、この機械を買っちゃおう!」とユーザーに思わせるほどの、強力な魅力を持ったコンテンツのことです。
現状、メタバースでできることというと、オンラインゲームや一部の人たちのコミュニケーションが中心になっている傾向があります。
例えば「Fortnite」や「Roblox」はゲームのプラットフォームとして絶大な人気を誇っていて、それ自体がメタバースのような楽しい体験を提供しています。
でも、ゲームにそれほど興味がない人たちをも惹きつけ「毎日でも遊びに行きたいな」と思わせるような、色とりどりのコンテンツが、まだまだ圧倒的に足りていないのが現状です。
多くの企業がメタバース上でイベントや展示会を開いていますが、その多くは現実世界のイベントを、ただ仮想空間に持ってきただけ、という印象が否めません。
「これって、別にメタバースじゃなくてもできるよね?」と思われてしまうような、本当の意味での「メタバースならでは」の感動体験を提供できているとは、ちょっぴり言いがたいかもしれません。一度参加すれば満足してしまい、なかなかリピーターにつながりにくいのです。
日常生活や仕事、勉強など、もっと幅広い分野で「これはメタバースじゃないとできない!」「メタバースの方が、断然便利で楽しい!」と感じさせてくれるような、新しくて質の高いコンテンツが生まれない限り、ユーザーの輪を広げていくのは難しいでしょう。
かつてスマートフォンが、たくさんの魅力的なアプリの登場によって、あっという間に私たちの生活に溶け込んでいったように、メタバースもまた、人々を惹きつけてやまない、独自のキラーコンテンツの登場が、今か今かと待たれているのです。
すごい!メタバースを上手に活用している企業のキラリと光る事例
多くの企業が試行錯誤する一方で、メタバースの持つ個性を上手に活かして、着実に素敵な成果を上げている事例も、ちゃんとあるんです。
これらの成功例を見てみると、主に「プロモーション」「ファンとの絆づくり」「お仕事の効率アップ」という3つの目的で、うまく活用されていることが分かります。
<プロモーション> 埼玉県の魅力を世界に!「バーチャル埼玉」
埼玉県は、県の魅力をたくさんの人に伝えるために、メタバース空間「バーチャル埼玉」をオープンしました。
さいたまスーパーアリーナや、風情ある川越の街並みなどをリアルに再現し、訪れた人は自分のアバターを通して観光地を巡ったり、イベントに参加したりできます。
これによって、特に若い世代の人たちに「埼玉って面白いかも!」と感じてもらう、素敵なきっかけ作りをしています。
移住の相談なんかも仮想空間でできるので、対面ではちょっと話しにくいことも、気軽に話せるような工夫がされています。
<ファンとの絆づくり> 写真好き、集まれ!富士フイルム「House of Photography in Metaverse」
富士フイルムは、写真やカメラを愛する人たちが集まるファンコミュニティとして「House of Photography in Metaverse」を公開しました。
ここでは、仮想のショールームで製品をじっくり眺めたり、セミナーで写真の技術を学んだり、他のユーザーさんと写真談議に花を咲かせたりできます。
時間や場所に縛られることなく、ファンとの温かくて深い絆を育むことに成功しているのです。
<お仕事の効率アップ> あのウォルマートも!VRで新人研修
世界最大のスーパーマーケットチェーンであるウォルマートは、従業員の研修にVRを取り入れています(参照:VRトレーニングを100万人の従業員へ ウォルマート、VRデバイス大量導入の理由)
特に、ブラックフライデーのような、お店が大混雑する繁忙期の様子をVRでリアルに再現し、とても実践的な接客トレーニングを行っているんです。
現実の世界ではなかなか準備が難しいシチュエーションでの対応力を、安全に、そして効率よく高めているというわけですね。
これらの事例に共通しているのは「メタバースで、何を達成したいか」という目的がとてもハッキリしている点です。
流行りに乗るだけじゃなく、メタバースが得意な「距離や時間を超える力」や「現実では難しい体験をさせてくれる力」を「うちの会社が抱えているこの課題を解決するために使えないかな?」と考えること。それが、成功への扉を開く鍵になりそうです。
これからの市場の成長と、メタバースが描く未来予想図
メタバースが今、たくさんの壁にぶつかっているのは事実です。でも、その未来については、多くの専門家が「まだまだこれからが本番だよ」と、温かいエールを送っているんです。
先ほどもお話ししたように、市場の大きさはこれから数年でグンと大きくなると予測されていて、その背景には、いくつかのワクワクするような成長の理由があります。
- 巨大IT企業たちの、本気の応援
- もっと身近に、もっと手軽に!進化するデバイスたち
- 仲間たちの成長が、メタバースをさらに面白くする
- 私たちの暮らしの変化が、追い風に
Meta社やApple、Microsoftといった巨大なテクノロジー企業は、メタバースを「次の時代の当たり前になるもの」と位置づけ、莫大な資金を注ぎ続けています。
彼らの本気は、新しいデバイスの進化や、ソフトウェア開発、面白いコンテンツ作りを加速させ、市場全体をグッと力強く押し上げてくれるはずです。
VR/ARデバイスは、年々小さく、軽く、そして高性能になっています。未来には、今のスマートフォンのように、もっと多くの人が気軽に買えて、サッと使えるようになると考えられています。
このデバイスがみんなの手に渡ることが、メタバースの仲間が増えるための、一番大切な要素の一つと言えるでしょう。
高速でたくさんのデータを送れる5Gや、その先の6G。本物みたいなグラフィックを生み出すCG技術。そして、人間のように自然におしゃべりできるAI。メタバースを支えるこうした仲間(関連技術)たちも、毎日ものすごいスピードで成長しています。
これらの技術が一つになることで、もっとドキドキするような、魅力的な仮想世界が作れるようになるのです。
リモートワークやお家からのオンラインでのコミュニケーションが当たり前になったことも、メタバースにとっては追い風です。私たちは、物理的な距離を超えて誰かとつながることに、もうすっかり慣れました。
仮想空間は、新しい出会いや、新しいビジネスが生まれる場所として、より自然に受け入れられる土壌が、少しずつ整ってきているんですね。
これらの理由から、メタバースは、一瞬で消える花火のようなブームではなく、長い時間をかけて、私たちの社会やビジネスのあり方を、根本から大きく変えるほどの可能性を秘めた技術だと言えるのではないでしょうか。
まとめ:メタバースの失敗から学ぶ、未来への成功の鍵
これまで、メタバースが直面しているちょっぴり手ごわい現実を一緒に見てきました。たくさんの「うまくいかなかった…」という経験談は、ちょっぴり耳が痛いかもしれません。でも、その一つひとつの経験は、未来の成功へと続く、かけがえのない道しるべなんです。
ここからは、そんな先輩たちのちょっぴり苦い経験から学んだ、「成功への鍵」を、一緒に見ていきましょう。
- まず「なぜ?」を大切にしよう
- 「誰に届けたい?」を深く考えよう
- 「ここでしかできない!」魔法をかけよう
- 焦らず、ゆっくり育てていこう
- まずは、小さな一歩から踏み出そう
- 自分たちにピッタリの「場所」を見つけよう
- 「おいでよ!」と、ドアを広く開けておこう
- 「また来たい!」と思えるサプライズを続けよう
- みんなが安心して遊べる「ルール」と「安全」を
- 夢とそろばん、両方を大切に
- 社内に「応援団」をつくろう
- 失敗は、次の成功へのチケット!
- 技術の「今」を、ちゃんと見つめよう
- みんなの「声」に、耳をすまそう
- メタバースの感動を、リアルな世界へつなげよう
「どうして私たちは、メタバースをやってみたいんだろう?」その気持ちを、まず自分たちではっきりさせることが、最初の、そして一番大切な一歩です。「商品のことをもっと知ってほしいな」「お仕事を少しでも楽にしたいな」「ファンのみんなともっと繋がりたいな」みたいに、目指すゴールを具体的に描いてみましょう。
「この感動を、一体誰に届けたいんだろう?」その人の顔を思い浮かべながら、どんな価値をプレゼントしたいのかを、じっくり考えてみませんか。その人が本当に「嬉しい!」「楽しい!」と感じてくれるような体験をデザインすることが、心をつかむ秘訣です。
現実の世界をただ真似するだけじゃ、もったいない!仮想空間だからこそできる、夢のような体験を創り出しましょう。距離や時間を飛び越えておしゃべりしたり、日常では絶対に味わえないようなドキドキする体験を提供したり。それがメタバースの本当の魅力です。
すぐに結果が出なくても、焦らないで。一瞬の話題作りだけを追いかけるのではなく、みんなが自然と集まり、長く居たくなるようなコミュニティを、時間をかけてじっくり育てていく。そんな農家さんのような視点が大切です。
最初から大きなお金をかけて壮大な計画を立てるのではなく、まずは小さな実験室のような場所で始めてみましょう。来てくれた人たちの反応を優しく見守りながら、少しずつ良くしていく。そうすれば、大きなリスクを抱えることなく、着実に前に進めます。
自分たちの目的や、届けたい相手に合った「場所(プラットフォーム)」を、丁寧に選ぶことも忘れずに。どんな機能があって、どんな人たちが集まっているのかをしっかりリサーチしましょう。せっかく素敵なお店を開いても、人通りの少ない場所では寂しいですもんね。
「特別な機械がないと入れません」なんて言われたら、がっかりしちゃいますよね。パソコンやスマートフォンからでも、誰でも気軽に「ちょっと覗いてみようかな」と思えるように、入り口のドアは広く開けておきましょう。操作も、初めて来た人でも迷子にならないように、分かりやすくシンプルにするのが優しさです。
いつ来ても同じだと、だんだん飽きられてしまうかもしれません。定期的に新しいイベントを開いたり、面白いコンテンツを追加したりして、「次はなんだろう?」とワクワクさせることが大切。みんなが自分で何かを作ったり、表現したりできる仕組みを取り入れるのも、とっても素敵ですね。
楽しい場所には、安心できるルールが必要です。個人情報のことや、著作権のことなど、守るべき法律やルールをしっかり守りましょう。誰もが心から安心して過ごせる環境を整えることは、主催者の大切な責任です。
素敵な夢を続けるためには、現実的な計画も必要です。「どうやってお金の流れを作るか」というマネタイズの方法を具体的に考えて、本当にそれが実現できるのかを、冷静に検証してみましょう。
この新しい挑戦は、一人ではできません。経営層の人たちにも理解してもらい、「いいね!やってみよう!」と会社全体で応援してくれるチームを作りましょう。専門知識を持った仲間を集めたり、育てたりすることも、プロジェクトを前に進める大きな力になります。
メタバースは、まだまだ生まれたばかりで、これからどんどん成長していく分野。試行錯誤は当たり前で、時には転んでしまうことも、きっとあります。でも、その失敗の一つひとつから積極的に学んで「次はこうしてみよう!」と次の一歩に活かす姿勢こそが、一番の成長の糧になります。
「いつか、あんなこともこんなこともできるはず!」と夢見るのは素敵ですが、過度な期待は禁物です。今の技術で「できること」と「まだ難しいこと」を冷静に見極めて、地に足のついた計画を立てましょう。
主役は、そこに集ってくれるユーザーの皆さんです。みんなとの対話を大切にして、「もっとこうだったらいいな」というフィードバックを、サービスの改善に優しく反映させていきましょう。
最終的に目指したいのは、メタバースの中だけで完結することではありません。メタバースでの楽しい体験や素敵な出会いが、現実世界でのお買い物につながったり、毎日の生活を豊かにしたり…。そんなふうに、仮想と現実の世界が素敵に手を取り合う未来をデザインすることが、本当のゴールなのかもしれませんね。